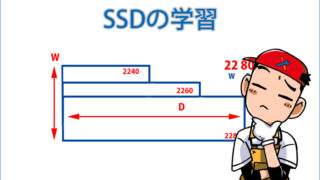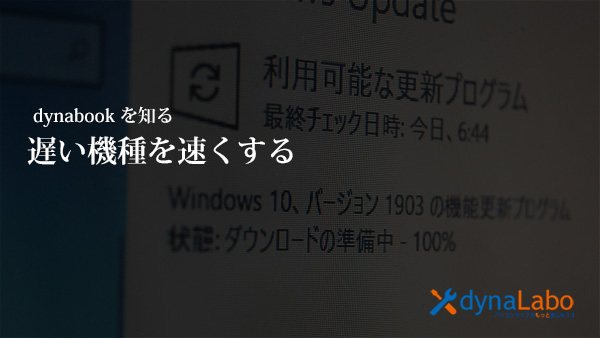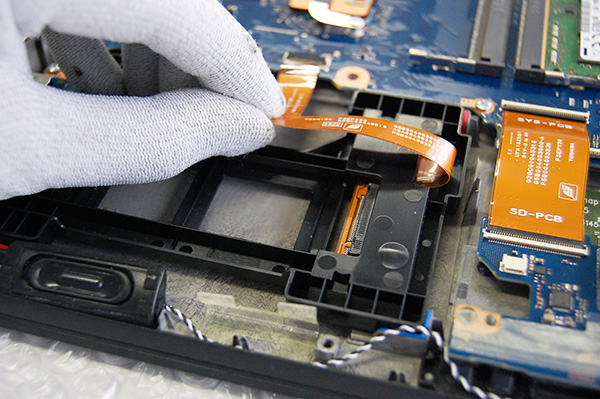windows10の操作遅延問題ではSSD換装が非常に効果的です。
起動時間、アプリのレスポンスなどが非常に良くなります。
最近はSSDユニット単体の価格もややHDD並みに近づきつつあるので今後はさらにSSD市場が拡大すると思いますよ
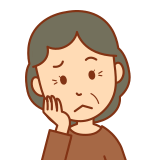
私にもできるかしら??

今回の調査メモではdynabook R73 or R73XシリーズのSSD接続を調べ、今後のSSD換装に役立てていきたいと思います。
接続方式
モバイルになると単に操作性を良くするだけではなく「軽量化」が必須です。
一般的には市販されえいる2.5インチのSSDを装着するケースが多いですが、モバイル型はそこに少し工夫をした方が良いです。

下記は2.5インチSSDですが、75gです。これも重い方と思います。
ちなみにHDDであれば80g~90gあります。

dynabook RX R730 R731シリーズ
このRX3シリーズがリリースされる頃はまだSSDというものが一般的ではなく、一部の機器(ipodなど)で搭載されいるのみだけでした。
東芝はそのSSDを作っていましたので、当然モバイルシリーズのカスタマイズモデルにも同じSSDが搭載されていました。
接続方式はLIFと言って24pin(SATA-LIF)
※SATA 第3世代です。
ZIFという40pin接続(SATA-ZIF)もありましたが、主にこれは日立系の接続のようで東芝LIFのようでした。

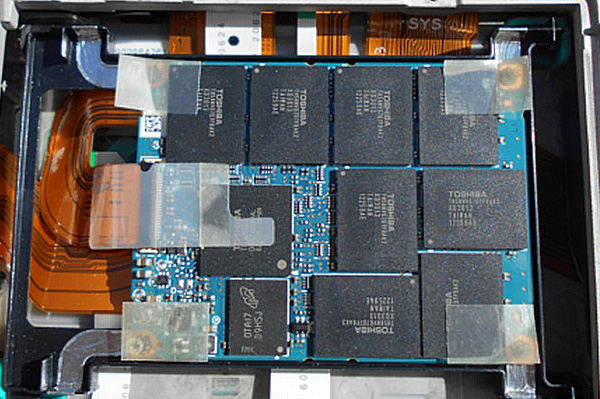

下記のフレキケーブルで接続されていて、赤矢印がマザー側にあり、SATAのケーブルと入れ替えが可能になっています。
今のようなSSDモジュールをコネクターに突っ込む形式ではなく、SSD自体にコネクターがあって、ケーブルを差し込みような形式でした。
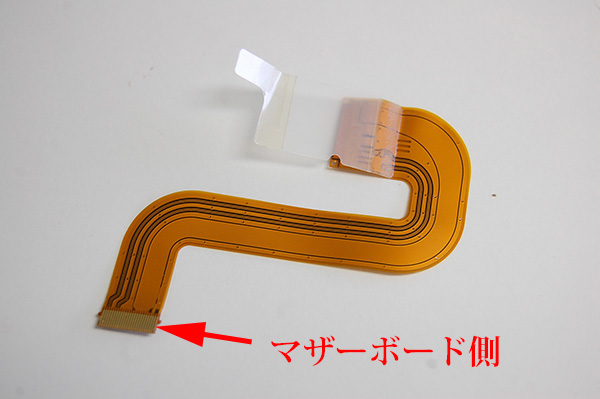
中にはこんなLIF型のSSDが入っています。

dynabook R732 R734シリーズ
このモデルになるとmSATAのSSD128GB及び256GBが使われています。

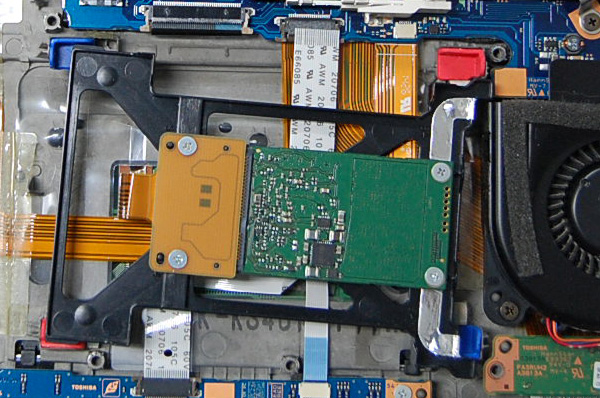
下記のフレキシブル(mSATA接続)が使われていて、コネクターをくるっと回して接続しています。
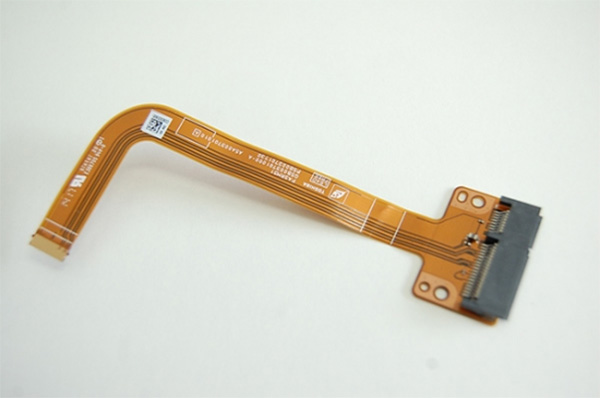
dynabook R73シリーズ
この頃になるとM.2タイプSSDが普及していますので、SATAのM.2が使われています。

下記がR73シリーズ専用SSDユニットです。
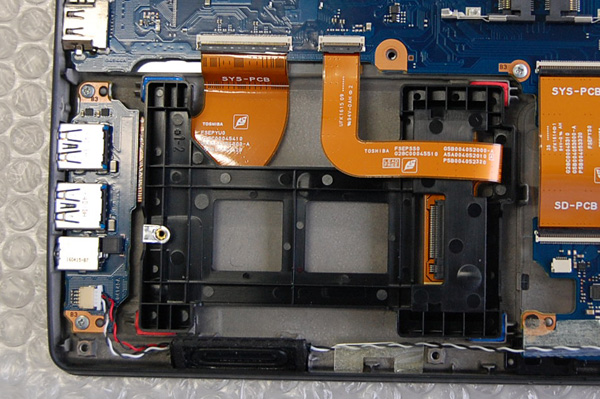
こんな感じでコネクター接続です。
このモデルはM.2の2280になります。

これもR734形式同様、SATAのフレキシブルケーブルとの入れ替えが可能になっています。
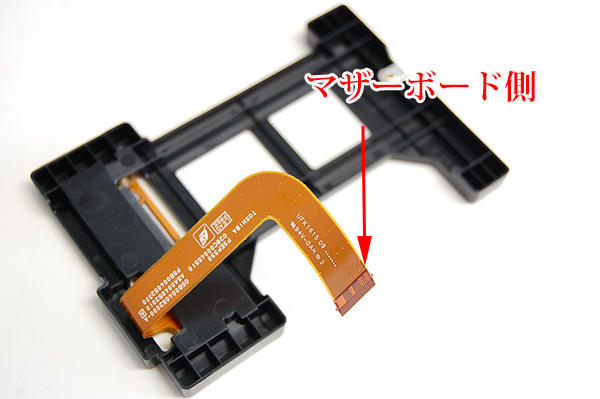
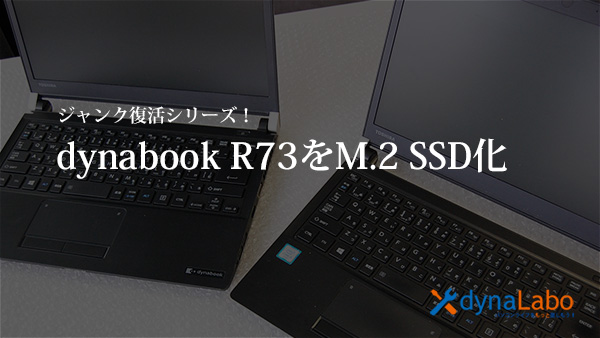
モバイルパソコンの場合、単にSSDだけ変えれば良いか?ではなく、「軽量化」にも徹底的に拘りたいです。
SSD装着ユニットが12gで本体のSSDが9gですから、合計で21gです。
2.5インチより軽いと思いますね。

以上

一言
2020年1月にはwindows7がサポート終了し、windows10への切り替えを余儀なくされると思いますが、その時に今ある機種をセルフメンテナンスでSSD化して欲しいです。
純正カスタマイズモデルになるとまだまだ高額ですが、自身で交換することでコストも削減できます。
windows7のモデルでもwindows10に再リカバリーをし、同時にSSDに変更することでパソコンが蘇ります。
スピード(レスポンス)と軽量化を同時に実現するには下記のようなM.2用のSATAアダプターにM.2のSSDを収納し、HDD用のフレキシブルケーブル(SATA)でするのが一番良いと思います。
コストも1万円前後でできると思います。

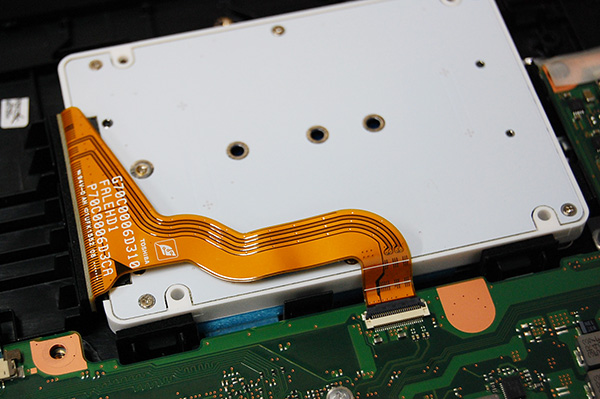
これであれば35gになりますので、HDDより50gは軽くなります。

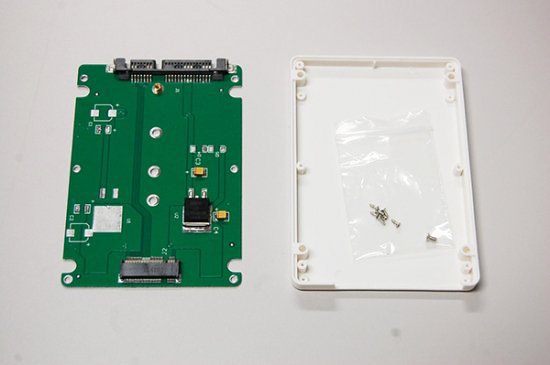
SSD参考情報